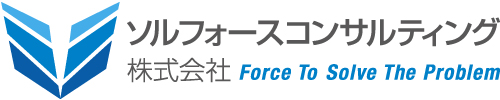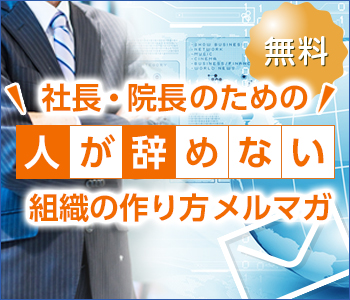今日は、クリニックを経営される先生にとって、少しドキッとするお話をさせていただきます。
先日も実際に支援させていただいている先生からこんなご相談がありました。
「ウチは採用してもスタッフが長続きしない」
「スタッフとも話し合った結果、この人ならいいんじゃないか、となり採用したものの、また1週間足らずで退職してしまった。最近、採用にトラウマになってね」
と随分お疲れのご様子。
退職されるスタッフに詳しく話を聞くと、
「リーダーが忙しく、いつもピリピリしていて相談しずらい」
「他の人に聞こうとしても、教えるとリーダーが気を悪くするからリーダーに聞いてと言われた。ここにいても働きづらいし、次の就職先に不利にならないために、就職はなかったことにして欲しい」とのことです。
そこで、リーダーに「なぜ新人を指導しないのか」と確認したところ、
「教えて下さいと言われていない。なぜ私を頼ろうとしないのか」と逆に気分を悪くされている始末。
これはリーダーだけが悪いのではありません。
スタッフの受け入れ態勢やリーダーの指導の仕方、職場風土に問題があります。
今の問題をそのままにしておけば、何人採用しても同じことです。
かといってリーダーだけに指導して解決する問題でもありません。
職場風土は仕組みで解決しなければ、根本的な解決になりません。
ここにこそ「人事評価制度の力」が大きく関係しています。
なぜ人事評価制度が「定着」「育成」に効くのか?
人事評価と聞くと、「給与の査定に使うもの」と思われがちですが、本当に効果のある評価制度は、「人を育てる」ための道しるべになります。
きちんと仕組みがあると、スタッフは「どうなれば評価されるか」「自分が目指すべき姿」が明確になります。
それが成長意欲や安心感につながり、結果的に医院に定着し、力を発揮してくれるのです。
評価制度があることで、感情や主観ではなく「基準に基づいた会話」が可能になります。
それによって、指導の軸がブレず、院長もスタッフも無駄に消耗せずに済みます。
「評価制度なんて、ウチにはまだ早い」と思っていませんか?
実際、評価制度というと「規模が大きい病院だけの話」と思われることもあります。
しかし、実際にはスタッフが3〜5名の小規模なクリニックほど、評価制度が大きく効果を発揮します。
なぜなら、小さな組織ほど「院長の感覚」で回してしまいやすく、それが原因でモチベーションの低下や誤解が生まれてしまうからです。
特に新しいスタッフが入ってくる時期や、組織の成長フェーズにあるクリニックにとっては、評価制度は「チームとしてまとまるための設計図」とも言えます。
あなたのクリニックでは、採用や定着で困っていることはありませんか。
目先のテクニックではなく、仕組みで根本解決が必要ですよ。
このようなことにご興味がある方のため、無料相談を実施しておりますので、ぜひご利用ください。